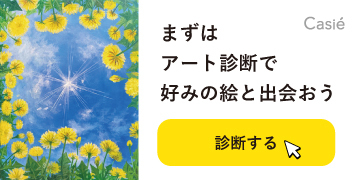四季の違いがはっきりしている日本。そして、昔から二十四節気と七十二侯といった自然と寄り添った生活に関する言葉があります。そのような季節の移ろいを感じながら、少しでも日々の生活を楽しめたらと思います。
小満
ゴールデンウイークも終わり、また日常の生活が始まりだしたころ、太陽の日差しが日に日に強まり、木々の緑が映え、五月晴れの爽やかな季節から梅雨が始まるぐずついた天気が続く頃。八節気となります。麦畑では麦の穂が実り、小さな満足が得られることから小満と言われるようになったという説があります。
現在の5月21日から6月4日日頃にあたります(暦により前後することがあります)

蚕起食桑
かいこおきてくわをくう。二十二侯にあたります。小満の初侯。
期間
5月21日から5月25日。
侯の意味
蚕が桑を盛んに食べ始める。
紅花栄
べにばなさかう。二十三侯にあたります。小満の次侯。
期間
5月26日から5月30日。
侯の意味
紅花が盛んに咲く。
麦秋至
ばくしゅういたる。二十四侯。小満の末侯。
期間
5月31日から6月4日。
侯の意味
麦が熟して麦秋となる。
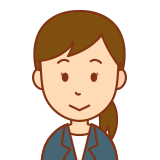
夏なのに秋がつくのは、麦が実ることを稲が実る秋に例えているからなのね。麦にとっての実りを迎える頃ということね。


小満の行事
衣替え
裏地の付いた袷(あわせ)から単衣(ひとえ)の着物や、綿や麻の薄地の生地で涼しい衣装に替えます。
元は心身の穢れを除く「物忌み」の日に行われる祓えの行事で、旧暦の4月1日と10月1日に「更衣」とよばれるしきたりがありました。
現在では、会社や学校では6月1日から上着を脱ぐ衣替えが行われていたが、温暖化の影響などで暑くなる時期が早まり、5月から移行期間が取り入れられる風潮が広まっている。
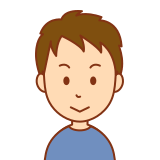
年々、上着を脱ぐのが早くなってきていますね。
でも、元々や冬服から夏服に衣替えするしきたりには意味があるって勉強になるね。
潮干狩り
干潟の浜辺で熊手などを使ってアサリ・ハマグリ・マテガイ・バカガイなどを捕る貝拾いは初夏から夏にかけての風物詩やレジャーとなっています。

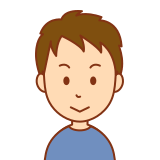
そろそろ、水の中に入って遊ぶのが気持ち良くなる季節ですね
小満に行われる祭り
三社祭り
東京浅草の浅草神社で行われる浅草神社例大祭。毎年、5月の第三金土日の3日間行われます。
浅草神社に祀られる3体の神様を三社様と呼ばれることから三社祭と呼ばれる。
初日は、浅草神社で「びんさら舞」を奉納。二日目は、大小100基の神輿が浅草の仲見世通りや浅草寺、浅草神社に向けて練り歩く。三日目は、「宮出し」が行われる。三体の神様が遷された3基の神輿が町を巡る。
この頃の生き物
植物
- 卯の花
- かきつばた
- 紅花
- 水芭蕉
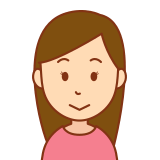
水辺に水芭蕉が咲き誇っている景色が目に浮かんできます
動物
- ほととぎす
- 蚕
- 鮎
- 鱒
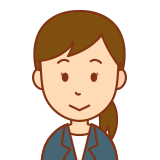
和菓子の若鮎が似合う季節ね
この頃のことば
走り梅雨
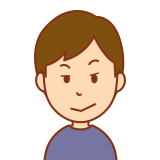
そろそろ、梅雨が近づいてきているね
この頃に使える時候の挨拶
- 気持ちのいい五月晴れがつづきますが
- 向暑のみぎりでございますが
- 衣替えの季節となりました。