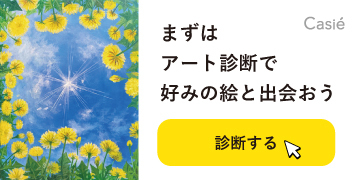四季の違いがはっきりしている日本。そして、昔から二十四節気と七十二侯といった自然と寄り添った生活に関する言葉があります。そのような季節の移ろいを感じながら、少しでも日々の生活を楽しめたらと思います。
立夏
夏の始まり初夏。旧暦の4月(卯月)5月(皐月)6月(水無月)が夏にあたります。七節気となります。春分と夏至の中間頃で、ゴールデンウイークの終盤で晴天の日が多く過ごしやすい爽やかな気候で、青空と新緑のコントラストが美しい時期です。
現在の5月5日から20日頃にあたります(暦により前後することがあります)

蛙始鳴
かえるはじめてなく。十九侯にあたります。立夏の初侯。
期間
5月6日から5月10日。
侯の意味
冬眠から目覚めた蛙が鳴き始める頃。
蚯蚓出
みみずいずる。二十侯にあたります。立春の次侯。
期間
5月11日から5月15日。
侯の意味
蚯蚓(みみず)が土の中から地上に這い出てくる頃。
竹笋生
たけのこしょうず。二十一侯。立夏の末侯。
期間
5月16日から20日。
侯の意味
地面から筍が生えてくる頃。

立夏の行事

端午の節句
男の子の健やかな成長を祝う日。
鎌倉時代の武家社会の中で、男の子の成長を願う日と変化し、江戸時代の頃には、現在のように鯉のぼりを掲げたり、鎧兜の武者人形を飾るようになったとされています。
菖蒲湯
5月5日の端午の節句の日に菖蒲の葉をお風呂に入れる行事。
菖蒲は病気に効く薬草として親しまれ、菖蒲湯に浸かることにより夏をしっかりと過ごせることが信じられていました。個人の風呂が無く、公衆浴場が一般的だった江戸時代に庶民に広まったとされます。
鵜飼
1300年の歴史がある岐阜県長良川の鵜飼いは5月11日に始まります。鵜匠が約10羽の鵜を操って篝火の下で鮎を捕ります。
立夏に行われる祭り

葵祭
5月15日に行われる京都三大祭りの一つ。平安時代に祭りといえば、葵祭をさしました。
元は賀茂祭りと呼ばれ、平安貴族の装束の人々や馬や牛車の行列が京都御所から上賀茂神社まで歩きます。行列の人々や道具などが、二葉葵の葉で飾られることから葵祭と呼ばれるようになりました。
神田祭
日本三大祭りの一つ。東京神田明神で隔年で5月の中旬に行われる。
徳川家康が戦勝祈願を行い、勝ったことから盛大に行われるようになりました。
この頃の生き物
植物
- 藤
- そら豆
- 筍
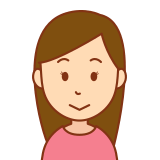
山や公園の中の藤棚が綺麗に咲いている頃が立夏の頃なのね
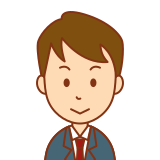
立夏の頃の夕方に、爽やかな風を浴びながら、そら豆や筍を肴にビールを飲んだら気持ちよさそうだね
動物
- 蛙
- ミミズ
この頃のことば
木の葉採り月・・・旧暦四月の異名。蚕に桑の葉を食べさせるために桑の葉を採ることから。
この頃に使える時候の挨拶
- 風薫る五月がやってまいりました。
- 青葉繁れる季節を迎え
- 八十八夜も過ぎ、夏の訪れを感じる頃となりました。
- さわやかな季節となりました。
- 新緑の美味しい季節となりました。
- 暦の上では夏となりました。
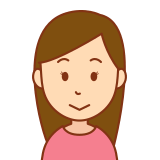
どの挨拶も爽やかな情景が思い浮かんできますね