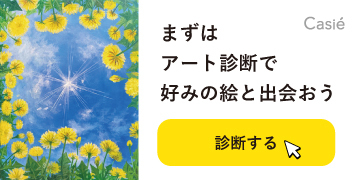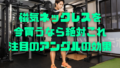四季の違いがはっきりしている日本。そして、昔から二十四節気と七十二侯といった自然と寄り添った生活に関する言葉があります。そのような季節の移ろいを感じながら、少しでも日々の生活を楽しめたらと思います。
立春
立春という名の通り、春の始まりであり、旧暦では新年の始まりの一月(正月)となります。二十四節気の一節気となり節気の一番最初です。暦の上では春とは言え、実際には一年で一番寒さの厳しい頃となりますが、徐々に寒さも和らぎ春の気配も感じられるようになります。
現在の2月4日から2月17日頃にあたります(暦により前後することがあります)
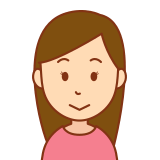
節分の次の日が立春。節分が一年の最後の日、大晦日であり、立春からが一年の始まりで正月でした。まだまだ寒い日が続きますが、春と聞くだけで心も体も、なんとなく暖かさが感じられますね。
立春の七十二侯
東風解凍
とうふうこおりとく。一侯にあたります。立春の初侯。
期間
2月4日から2月8日。
侯の意味
暖かい春風が吹き始めて、川や池の氷が解け始める頃。また、その魚が盛んに動き出し春の気配を感じる様子。
黄鶯睍睆

うぐいすなく。二侯にあたります。立春の次侯。
期間
2月9日から2月13日。
侯の意味
鶯が鳴き始める頃。鶯は、春告げ鳥とも言われ春の象徴である鳥。
魚上氷
うおこおりにあがる。三侯。立春の末侯。
期間
2月14日から2月18日。
侯の意味
川や池の氷が解けた割れ目から、魚が勢いよく飛び跳ねる様。魚の勢いに春を感じる。

立春の行事
秋田県横手市のかまくら
秋田県横手市で400年以上続く、水神様を祀る伝統的な行事。かまくらの中に、神棚を設け、甘酒や餅を焼いて振舞われる。

立春の頃の祭り
初午祭
稲荷神社で2月の最初の午の日に行われる祭り。元は、旧暦の二月の最初の午の日に行われていたが、現在では新暦の2月の最初の午の日に行われている。
祈年祭
その年の豊作を祈って全国の神社で行われる春の祭り。「きねんさい」または「としごいのまつり」と呼ばれる。
立春の頃の生き物・食べ物
植物
- 猫柳
- 梅
食べ物
- サザエ
立春の頃のことば
- 余寒見舞い・・・立春は春の始まりと同時に、旧暦では新年の始まりで一月。春とはいえ実際には寒い日が続き、春であるのに寒いことから余寒と呼ばれます。立春を過ぎて出す季節の挨拶のことを余寒見舞いといいます。
- 春一番・・・立春を過ぎて最初に吹く南からの風を春一番といいます。日本海側を通過する低気圧に向かって南から暖かい空気が流れ込み春一番になります。
立春の頃に使える時候の挨拶
- 余寒お見舞い申し上げます。
- 三寒四温の時節、
- 立春とは名ばかりの寒さが続いておりますが、
- 寒さの中に春の兆しが感じられる頃となりました。
- 日差しもほんの少しずつ暖かく、