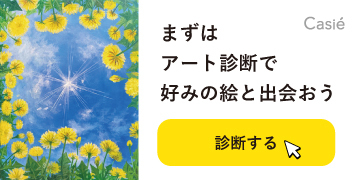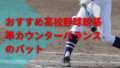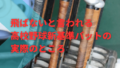四季の違いがはっきりしている日本。そして、昔から二十四節気と七十二侯といった自然と寄り添った生活に関する言葉があります。そのような季節の移ろいを感じながら、少しでも日々の生活を楽しめたらと思います。
大寒
大寒という名の通り、一年で一番寒い時期になりやすいことを表しています。二十四節気となり節気の一番最後で、次の節気は立春となり新しい一年、春の始まりとなります。
現在の1月20日から2月3日頃にあたります(暦により前後することがあります)
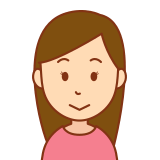
二十四節気の最後の節気が大寒で冬の最後となります。ただし、まだまだ寒い日は二月まで続き、春の訪れを感じるのは三月まで待たなければなりませんね。
大寒の七十二侯
款冬華
ふきのとうはなさく。七十侯にあたります。大寒の初侯。
期間
1月20日から1月24日。
侯の意味
厳しい寒さの中、ふきのとうの蕾が出る頃。
水沢腹堅
みずさわあつくかたし。七十一侯にあたります。大寒の次侯。
期間
1月25日から1月29日。
侯の意味
沢の水が凍るほど寒さの厳しい頃。
鶏始乳
にわとりはじめてにゅうす。七十二侯。大寒の末侯。
期間
1月30日から2月3日。
侯の意味
春の訪れを感じた鶏が卵を産み始める頃。冬の終わりの兆し。

大寒の行事
節分
節分といえば2月の節分を思い浮かべる人が多いと思いますが、本来は、立春・立夏・立秋・立冬の前日のことを節分といいます。すなわち、各季節の分かれ目という意味です。
立春の前日の節分は旧暦では、大晦日。平安時代には宮中で、この日に追儺という行事が行われていました。追儺とは、方相氏という役目の人が鬼を追い出すために宮中を回る儀式で、これが転じて、鬼を追い出す豆まきの起源になったと考えられています。

豆まき
節分に豆まきをするのは季節の変わり目に鬼が現れ邪気をばらまくと考えられていたから。鬼を追い払うために豆をまくのは、魔を滅すが魔滅、まめ、豆につながるから。豆をまいて、魔を滅す、鬼や悪霊を追い払うという願いが込められています。
ひいらぎ鰯
節分の日には、家の玄関に焼いた鰯の頭をひいらぎにさして魔除けとして飾ります。鰯の匂いを鬼が嫌うことと、ひいらぎの葉の先が鬼の眼に刺さるようにという意味合いを持っています。

恵方巻
節分の夜に、その年の恵方の方を向いて海苔巻き一本を丸被りしながら黙って食べきるという風習。一年間の無病息災を願っていると食べられる。切らずに食べるのは、縁を切らないという意味を持つと考えられている。一般的に広まったのは、関西を中心に昭和の終わりごろからとされていますが、大阪などでは古くから商人の間で行われていたなどの説があります。

大寒の頃の生き物・食べ物
植物
- 椿
- 南天
- ふきのとう
- 福寿草
食べ物
- ワカサギ
- 恵方巻
大寒の頃のことば
- 三寒四温・・・一般的には、3日間寒い日が続いた後、4日間暖かい日が続くという天候が繰り返されること。これは、春が近づいてくると大陸からの移動性高気圧が順々にやってくる気圧配置となり、高気圧の谷間の寒い日と高気圧の暖かい日が繰り返されることにより起こる。春の到来を感じさせる気候。
大寒の頃に使える時候の挨拶
- 正月気分もようやく抜け、
- 寒さが肌を刺す今日この頃でございますが、
- 今年は例年にない寒さとのことで、
- 暖冬とは申せ、吹く風はやはり冷たく、