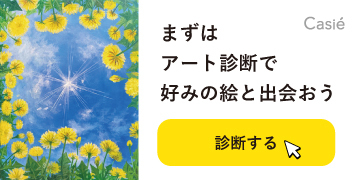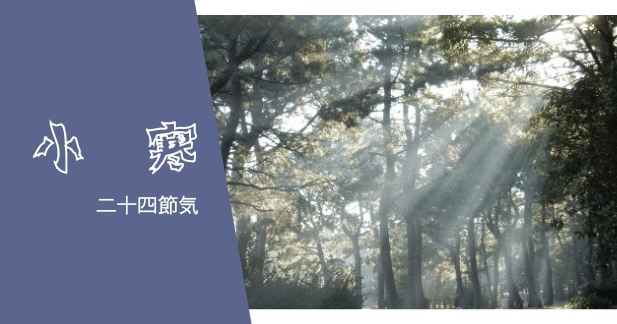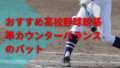小寒(しょうかん)は、二十四節気の一つであり、冬本番の寒さが始まる「寒の入り」を示す時期です。1月5日頃から1月19日頃までのこの期間、日本では防寒対策や健康管理が特に重要とされ、昔から寒さを活かした行事や伝統が受け継がれてきました。本記事では、小寒に関連する行事や食べ物、そして寒さを乗り切る生活の知恵について詳しく解説します。冬を快適に過ごすヒントを見つけて、季節の移ろいを楽しんでみませんか?
小寒とは何か
小寒の概要
小寒(しょうかん)は、二十四節気の一つであり、1月5日頃から1月19日頃までを指します。この時期は「寒の入り」とも呼ばれ、冬本番の寒さが始まるとされています。暦の上では冬の中盤に位置しますが、実際には最も寒い時期が近づく季節です。日本では、この期間を中心に寒稽古や寒中見舞いなど、寒さに関連した行事が行われることがあります。
小寒の意味や起源を説明
小寒という名称は、寒さが増し始める時期を表現したものです。中国で作られた二十四節気の中で、季節の変化をより細かく分けるために名付けられました。日本でも古くからこの暦が用いられ、農業や生活の指針として親しまれてきました。小寒が「寒の入り」とされるのは、次の節気である「大寒」に向けてさらに厳しい寒さが続くからです。
二十四節気における位置づけ
二十四節気は、一年を24の季節に分け、それぞれに名前を付けたものです。その中で小寒は、冬至の次に訪れる節気であり、「寒の内」という寒さのピーク期間の始まりを告げる重要な位置づけとなっています。小寒の次に控える「大寒」が一年で最も寒い時期とされるため、小寒はその準備期間とも言えます。また、この時期には自然界の活動が静まり、春に向けたエネルギーを蓄える季節でもあります。
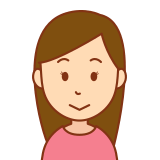
これからが本格的な冬の寒さが続く頃となってきます。庭の水が凍っていたり、雪の降る日が増えたりしてきます。また、正月の後の行事もたくさんあり、新年のにぎわいの余韻が続く頃でもあります。
小寒の七十二侯
芹乃栄
せりさかう。六十七侯にあたります。小寒の初侯。
期間
1月5日から1月9日。
侯の意味
寒さが厳しくなる中で、冷たい水が流れる沢で芹が生い茂っていく頃。
水泉動
すいせんうごく。六十八侯にあたります。小寒の次侯。
期間
1月10日から1月14日。
侯の意味
地面の中で凍っていた泉の水が動き始める頃。
雉始雊
きじはじめてなく。六十九侯。小寒の末侯。
期間
1月15日から1月19日。
侯の意味
雉のオスがメスを求めて鳴き始める頃。繁殖活動を始める春が近づいている。

小寒に関連する行事
日本各地の伝統的な行事(例:寒稽古、寒中見舞いの習慣)
小寒の時期は、寒さを活かした伝統的な行事が日本各地で行われます。その代表的なものが「寒稽古」です。寒稽古とは、剣道や柔道、空手などの武道や書道、茶道などで、厳しい寒さの中で修行や稽古を行う習慣を指します。冷たい空気の中で心身を鍛えることが目的であり、精神力や集中力を高める重要な機会とされています。
また、「寒中見舞い」の習慣も小寒に関連しています。寒中見舞いは、小寒から大寒にかけての厳しい寒さの中、相手の健康を気遣う挨拶状を送る日本の伝統的な風習です。年賀状を送りそびれた場合や喪中の場合にも用いられることがあり、季節の節目を感じさせる風物詩となっています。
神社や地域の特別な催し物
小寒の時期には、神社や地域で特別な催し物が行われることもあります。たとえば、寒さの中で行う神事や祭りでは、厳しい自然に感謝し、新年の無病息災や豊作を祈願する行事が一般的です。代表的なものとして、寒中禊(みそぎ)が挙げられます。これは、冷たい川や海に入って身を清める儀式で、厳しい寒さに耐えることで心身を浄化し、新しい年を清らかな気持ちで迎えるという意味があります。
地域によっては、小寒から大寒の間に行われる「寒餅つき」も見られます。これは、厳しい寒さの中で餅をつくことで、保存性が高まるとされる昔ながらの知恵に基づいています。こうした催し物は、地域の伝統や文化を守りながら、寒い季節を乗り切るための工夫を象徴しています。
鏡開き
お正月に飾っていた鏡餅を下げて、食べやすい大きさにしていくことですが、歳神様にお供えをして餅には神様が宿っていると考えられるので、切るや割るなどの言葉を使わずに開くと表現されます。鏡開きの日は、地方によって異なりますが一般的には1月11日とされることが多いです。神様が宿っている餅を食べることで身体に神様を取り入れるという考えや、固い餅を食べることで歯固めをして長寿を願うという考えが込められています。
初釜
新年最初のお茶会や茶の稽古始めを初釜といいます。新年の挨拶が終わった10日前後に客人を呼んで、元日に酌んだ若水で湯を沸かしお茶を振舞います。
成人式
その年度に20歳を迎える若者の成人を祝う儀式。2000年以降は、1月の第二月曜日が「成人の日」の祝日と定められている。2022年から法律上の成人は18歳とされたので、「成人式」という呼称ではなく「20歳(はたち)の集い」という呼称で各自治体ごとに儀式が行われるようになってきている。古くは15歳を成人として、それを祝う「元服」の儀式が1月15日に行われていた。

小正月
旧暦の1月15日は新年初めての満月の日であり、この日を正月に対して小正月として祝われた。正月疲れを癒したり、農作業道具や職人の道具を手入れして奉納し、一年の豊作や繁盛を祈念したり、成人を祝う元服が行われたりした。小正月には、小豆を入れた小豆粥を食べて一年の健康と厄除けを願った。
とんど焼き・左義長
正月の注連飾りや門松、書初めや古いお札などを神社の境内や田んぼで炊き上げる行事。小正月である1月15日に行われる。この煙に乗って歳神様が帰られると考えられ、また、この火で焼いた餅を食べたり煙を浴びることで一年が健康に過ごせるとも考えられている。地域によって、「とんど焼き」「どんど焼き」「左義長」などと呼び名は異なる。もとは、宮中で行われた陰陽道の悪魔払いの儀式とされる。

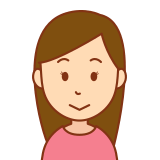
小寒の行事は、寒さを厳しいだけでなく、心身を鍛えたり、地域のつながりを深めたりする機会として捉える、日本ならではの文化が息づいています。
小寒の食べ物
旬の食材や料理(例:大根、白菜、里芋を使った鍋料理)
小寒の時期は、冬野菜が最も美味しい季節です。特に大根、白菜、里芋などは寒さによって甘みが増し、煮物や鍋料理にぴったりの食材です。これらの食材を使った鍋料理は、体を芯から温めるだけでなく、栄養価も高く、寒い冬を乗り切るための理想的なメニューです。例えば、豚肉と白菜のミルフィーユ鍋や、大根を使ったおでんは、小寒におすすめの料理です。また、里芋を加えた味噌煮込みは、ほくほくした食感が楽しめる一品です。
小寒に食べると良いとされる縁起物の食べ物(例:金柑、七草粥)
小寒には、縁起物として特別な意味を持つ食べ物を取り入れる習慣もあります。金柑は、小さな実にたっぷりのビタミンCが含まれており、風邪予防に役立つ食材です。その黄金色の実は、金運や幸福を象徴するとも言われ、小寒に食べると縁起が良いとされています。
また、小寒の終わり頃(1月7日)に食べる七草粥は、無病息災を祈る伝統的な料理です。セリ、ナズナなどの七草が入った粥は、胃腸に優しく、年末年始で疲れた体を癒やす効果も期待できます。この時期にしか味わえない行事食として、多くの家庭で親しまれています。
七草粥
七草粥を食べる1月7日は、人日の節句とされます。春の七草(セリ・ナズナ・ハコベラ・ゴギョウ・スズシロ・スズナ・ホトケノザ)を入れたお粥を食べると邪気を払い万病に効果があるという言い伝えがあります。また、お節料理で疲れた胃を休ませ野菜を摂ることで栄養補給をするという側面もあります。七草は、本来は野原に生えているものを摘んで食べられる食材でしたが、現在はスーパーなのでもセットになって売られています。

冬の栄養補給に適したレシピ提案
小寒の時期は寒さが厳しく、体温を維持するためのエネルギーが必要です。そのため、栄養価の高い料理を取り入れることが大切です。以下のレシピは、小寒におすすめの冬の栄養補給メニューです:
金柑の甘露煮:デザートとして楽しめる金柑の甘露煮は、ビタミン補給に最適で、小寒の縁起物としてもおすすめ。
しょうが入り鶏団子鍋:鶏肉としょうがを使った鍋は、体を温める効果抜群。ネギや春菊を加えてビタミンを補給。
里芋と大根の豚汁:根菜をたっぷり使った豚汁は、寒い日の定番。味噌の発酵食品効果で免疫力アップ。
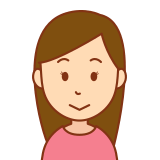
小寒の食べ物は、旬の味覚や健康に役立つ食材を楽しみながら、寒い季節を乗り切る知恵が詰まっています。これらの料理を食卓に取り入れることで、体も心も温かく過ごせるでしょう。
小寒の祭り
十日戎
戎を祀る神社で行われる新年初の祭り。関西の戎神社で盛ん。9日・10日・11日の3日間で行われ、9日を宵えびす、10日を本えびす、11日を残り福と呼ぶ。参拝者は、福笹に小判・鯛・俵・小槌などの縁起物を授かり一年間の商売繁盛を祈念する。大阪の今宮戎神社や兵庫県の西宮神社の祭りが有名である。

小寒の過ごし方と生活の知恵
防寒対策のポイント(衣類、住まいの工夫)
小寒の時期は寒さが本格化するため、防寒対策が欠かせません。衣類では、インナーに保温性の高い素材を選び、首元や手首、足首をしっかり温めるのがポイントです。特にウールやヒートテック素材の重ね着は、冷えを防ぎつつ動きやすさを保てます。また、帽子や手袋、マフラーなどの小物も活用しましょう。
住まいの防寒対策としては、窓やドアの隙間風を防ぐための断熱シートやカーテンを使用することが効果的です。さらに、足元を冷やさないために厚手のラグや床暖房を取り入れるのもおすすめです。湯たんぽや電気毛布を活用して寝る前に布団を温めることで、快適な睡眠環境を整えられます。
冬特有の健康管理(例:風邪予防の方法、体を温める食事や飲み物)
寒さが厳しい小寒の時期は、風邪やインフルエンザのリスクが高まるため、健康管理が重要です。風邪予防には、手洗いやうがい、加湿器を使った室内の湿度管理が基本です。また、適度な運動や日光浴を心がけ、免疫力を高めることも大切です。
体を温める食事や飲み物としては、しょうがやにんにく、唐辛子を使った料理が効果的です。例えば、しょうが入りのスープやにんにくの効いた鍋料理は、冷えた体を芯から温めてくれます。飲み物では、しょうが湯やホットレモン、甘酒などが人気です。これらはビタミンやミネラルも補給でき、寒さによる体調不良を防ぐ助けとなります。
小寒から大寒までの「寒仕込み」の伝統
小寒から大寒にかけては「寒仕込み」と呼ばれる伝統的な保存食の仕込み時期です。この時期の寒さは雑菌の繁殖を抑えるため、味噌や醤油、日本酒などの発酵食品の仕込みに最適とされています。特に味噌の寒仕込みは、昔から日本の家庭で行われてきた習慣で、冬の厳しい気候が味を深めると言われています。
また、寒餅つきも寒仕込みの一環です。寒中に作られた餅は日持ちが良く、風味が増すため、特別な縁起物として扱われてきました。現代では、家庭で行う機会が減ったものの、地域の行事や専門店でこの伝統を体験することができます。
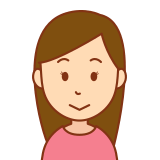
小寒の過ごし方は、寒さを乗り切る知恵と工夫に満ちています。衣食住の工夫を取り入れることで、快適に冬を楽しみながら、健康的に過ごすことができるでしょう。
小寒の頃のことば
- 寒の入り・・・小寒を迎える頃から本格的な寒さがやってきます。このことを寒の入りといいます。また、寒中見舞いの挨拶を出し始める頃でもあります。
小寒の頃に使える時候の挨拶
- 本格的な冬の到来を迎え、
- 早いもので松の内も空けて、
- おだやかな初春を家族でお迎えのことと存じます。
まとめ
小寒は、寒さが本格化する時期であり、日本の生活や文化に深く根付いた節気です。寒稽古や寒中見舞いといった行事を通じて、寒さを逆手に取った精神的な成長が図られてきました。また、旬の食材や縁起物を取り入れた食事、寒仕込みの伝統など、この季節ならではの楽しみ方も豊富です。防寒対策や健康管理の工夫を取り入れながら、厳しい冬を心温まるひとときに変えていきましょう。小寒の知恵を活かして、次の節気である大寒、そして春の訪れを迎える準備をしてみてください。