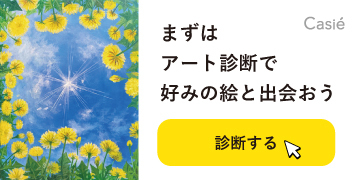四季の違いがはっきりしている日本。そして、昔から二十四節気と七十二侯といった自然と寄り添った生活に関する言葉があります。そのような季節の移ろいを感じながら、少しでも日々の生活を楽しめたらと思います。
小雪
冬の典型的な気圧配置である西高東低の気圧配置が見られるようになり、風も北風が吹き始めます。日本海側では初雪が見られることも。冬支度を始めだす頃となります。二十節気となります。
現在の11月22日から12月6日頃にあたります(暦により前後することがあります)
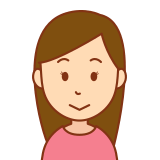
外にいると北風の冷たさを感じ始める頃で冬の到来を感じさせます。

小雪の七十二侯
虹蔵不見
にじかくれてみえず。五十八侯にあたります。小雪の初侯。
期間
11月22日から11月26日。
侯の意味
太陽の高度も低くなってきて空気も乾燥し始めると虹が発生しにくくなってくる頃。
朔風払葉
さくふうはをはらう。五十九侯にあたります。小雪の次侯。
期間
11月27日から12月1日。
侯の意味
日増しに強くなりつつある北風により、赤や黄色に色づいた落ち葉が吹き払われる頃。

橘始黄
たちばなはじめてきなり。六十侯。小雪の末侯。
期間
12月2日から12月6日。
侯の意味
橘の実や葉が黄色く色づき始める頃。橘そのものの意味と、ミカン類の総称として橘という説もある。

小雪の行事
勤労感謝の日
勤労を尊び、生産を祝い、国民がたがいに感謝しあうことを趣旨に1948年に祝日と制定された。11月23日は新暦では新嘗祭の日にあたる。
お歳暮
一年間のお世話になった方々への感謝の気持ちを込めて品物を贈答すること。正月を迎える前の年末の忙しい時期に差し掛かってくる頃でもあるので、塩鮭や数の子など正月に役立つ品物を送るのが一般的な慣わしである。

小雪に行われる祭
新嘗祭
天皇がその年に収穫された穀物(米)への感謝し宮中でお供えし、それを食する儀式。旧暦では11月の第二卯の日に行われていたが新暦では11月23日に行われる。現在は勤労感謝の日として祝日となっているが、それまでは新嘗祭の祝日であった。天皇が即位後に初めて行われる新嘗祭を大嘗祭と呼ぶ。
秩父夜祭
秩父神社で行われる例大祭で、祇園祭・高山祭と並んで日本三大美祭とされています。
秩父神社の女神と武甲山の男神が年に一度の逢瀬を祝う祭とされ、20トンにもなる山車が急な団子坂を引き上げられる様は圧巻な祭りの風景となっています。

小雪の頃の生き物・食べ物
植物
- 橘

食べ物
- 鱈
- 蓮根
- 南瓜
- 白菜
- 牡蛎
小雪の頃のことば
- こたつ開き・・・文字通り、こたつを出す日のこと。旧暦10月の亥の日に出す風習があるのですが最初の亥の日は武家が、庶民が二回目の亥の日とされたりしました。10月の最初の亥の日は立冬に来ますが、二回目の亥の日は小雪になることもありました。最近は、立冬では早すぎるので、小雪の時期に出すことの方が多いのではないでしょうか。

小雪の頃に使える時候の挨拶
- 野も山も色づき始め、
- 秋もたけなわでございますが、
- そろそろ、紅葉も楽しめる季節となりました。
- 木々の梢も色づいて
- 秋色日ごとに深まり、