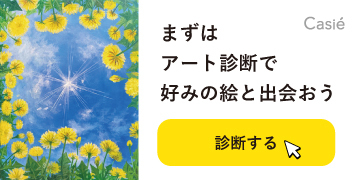四季の違いがはっきりしている日本。そして、昔から二十四節気と七十二侯といった自然と寄り添った生活に関する言葉があります。そのような季節の移ろいを感じながら、少しでも日々の生活を楽しめたらと思います。
立冬
旧暦では10月にあたる神無月からが冬の季節の始まり。木々の色づきも最高潮を迎え、散り始めも。日に日に気温も下がっていき、冬の到来を感じ始める頃となります。十九節気となります。
現在の11月7日から11月21日頃にあたります(暦により前後することがあります)
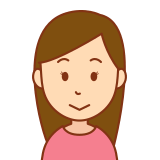
朝晩の寒さが感じられるようになり、吐く息が白くなる日も。日中は穏やかな過ごしやすい日が続きますが、そろそろコタツの準備など始める家も多いのではないでしょうか。

立冬の七十二侯
山茶始開
つばきはじめてひらく。五十五侯にあたります。立冬の初侯。
期間
11月7日から11月11日。
侯の意味
つばきの花が咲き始める頃。ここで言うつばきは、山茶花(さざんか)のこと。
地始凍
ちはじめてこおる。五十六侯にあたります。立冬の次侯。
期間
11月12日から11月16日。
侯の意味
朝夕の冷え込みが厳しくなり地面が凍てつき始める頃。
金盞香
きんせんこうばし。五十七侯。立冬の末侯。
期間
11月17日から11月21日。
侯の意味
キンセンカの花が咲き始める頃。

立冬の行事
七五三

子どもの成長を祝って神社にお参りをする行事。男の子は、三歳と五歳。女の子は、三歳と七歳にお参りする。男の子は五歳の時に、袴着といって初めて袴を穿いたり、女の子は三歳の時に髪置として今まで剃っていた髪の毛を伸ばし始め、七歳の時には帯解として本格的な帯を締め大人の仲間入りという節目をもっている。七歳まで無事に成長したことへの感謝の願いも込められている。江戸時代に広まった。
千歳飴
七五三の時に、鶴亀や松竹梅の絵柄が入った袋に入った長細い飴。飴の長さが、子供の長寿を願う縁起物として、七五三で食べると良いとされている。金太郎飴のように絵柄が入っている場合が多い。

酉の市
11月最初の酉の日に寺社の門前で開かれた市が酉の市。月に二度が三度あるので、それぞれ一の酉、二の酉、三の酉と呼ばれる。市では熊手を買うと福をかき集めるという意味から縁起が良いとされ、値切って買い、値引き分を店主に返す買い方が粋とされる。また、店主から威勢の良い掛け声と手締めが行われる。一方、三の酉がある年は火事が多いという言い伝えもある。

立冬の頃の生き物・食べ物
植物
- 山茶花
- 水仙
食べ物

- 蟹
- ふぐ
- くえ
立冬の頃のことば

- 木枯らし一号・・・立冬を過ぎて、その年初めて吹く北風を木枯らし一号と呼ぶ。木枯らしが吹き始めると本格的な冬の到来と考えられる。
- 小春日和・・・晩秋から初冬にかけての春のような穏やかな暖かい日のこと。小春とは、旧暦10月の異称。
立冬の頃に使える時候の挨拶
- 秋気いよいよ深く、
- うららかな菊日和がうれしい昨今、
- 鮮やかな紅葉の季節となりました。
- 朝晩ひときわ冷え込むようになりました。