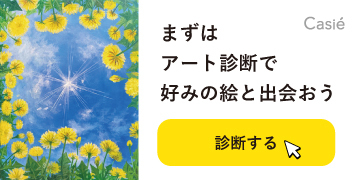四季の違いがはっきりしている日本。そして、昔から二十四節気と七十二侯といった自然と寄り添った生活に関する言葉があります。そのような季節の移ろいを感じながら、少しでも日々の生活を楽しめたらと思います。
秋分
お昼の長さと夜の長さがちょうど同じになる日です。これは、太陽がちょうど赤道上を通過するために日の出から日の入りまでの時間が地球の自転の半分になるからです。その結果、太陽は真東から日の出があり、真西に日の入りします。秋分を過ぎると日の出日の入りの位置が南側にずれていき、徐々に夜の時間の方が長くなっていきます。十六節気となります。
現在の9月23日から10月7日頃にあたります(暦により前後することがあります)
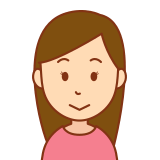
秋分の日を過ぎると日に日に日の入り時間が早くなり暗くなっていくのが早くなって物悲しさを感じるようになりますね。

秋分の七十二侯
雷乃収声
かみなりこえをおさむ。四十六侯にあたります。秋分の初侯。
期間
9月23日から9月27日。
侯の意味
この頃から雷の鳴る回数が減っていく。
蟄虫坏戸
すごもりのむしとをとざす。四十七侯にあたります。秋分の次侯。
期間
9月28日から10月2日。
侯の意味
土の中の虫たちが穴をふさぎ、外に出てこなくなる。虫たちは季節の変化を感じ取り冬ごもりを始めている頃。
水始涸
みずはじめてかれる。四十八侯。秋分の末侯。
期間
10月3日から10月7日。
侯の意味
稲刈りの準備のために田んぼの水抜きをする頃。

秋分の行事
社日
秋分の日に一番近い戌の日のこと。秋の収穫の目安とされる日で、土地の農業神にお参りして、収穫物をお供えして感謝を伝える日とされます。春の社日に降りてきた神様は、この日に天に帰るとされています。
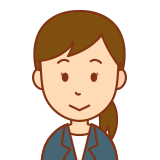
社日という日があるのを初めて知りました。農家の人にとっては大切な日なんですね。
衣替え
夏の衣装から冬の衣装に替える日。一般的には、10月1日とされるが最近は暑さが続くことが多くなり適宜実施されることが多い。旧暦の10月1日は現在の11月頃に当たるので旧暦では季節的にちょうど適した頃合いだったのではないでしょうか。元は、宮中で夏装束から冬装束に替えられていた行事。
秋の七草
萩・薄(ススキ)・桔梗・撫子(なでしこ)・葛・藤袴・女郎花の7つの植物。

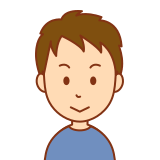
春の七草は食用とされていますが、秋の七草は観賞用の花ですね。
秋分の頃の生き物・食べ物
植物
- リンドウ
- 彼岸花
- あざみ

食べ物
- おはぎ
- 松茸
- 秋刀魚
- 栗

秋分の頃のことば
- 暑さ寒さも彼岸まで・・・9月になっても残暑が厳しかったのが秋分の頃になると、朝晩の気温だけでなく昼間の気温も徐々に過ごしやすくなってきます。この言葉の彼岸は春と秋の両方を指しますが、秋の場合は暑さも彼岸までということになります。
秋分の頃に使える時候の挨拶
- 秋風が心地よい季節となり、
- 日増しに秋の気配を感じる頃となりました。
- 庭の柿の実が色づき始めました。