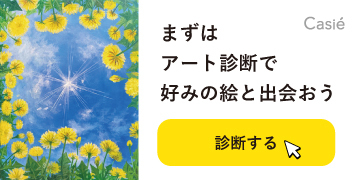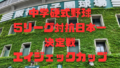四季の違いがはっきりしている日本。そして、昔から二十四節気と七十二侯といった自然と寄り添った生活に関する言葉があります。そのような季節の移ろいを感じながら、少しでも日々の生活を楽しめたらと思います。
白露
白露から中秋に入っていき日の入りも日に日に早くなるように感じられ秋が深まっていきます。朝夕の涼しさから草花の葉に露が付くようになることから白露と呼ばれます。十五節気となります。中秋の名月と呼ばれるように、この時期の満月(十五夜)の日がお月見にあたる中秋の名月となります。
現在の9月7日から9月22日頃にあたります(暦により前後することがあります)
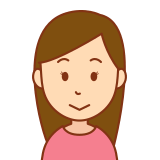
お昼の間はまだ夏のように暑いですが、夜になるとどこからともなく虫の鳴き声が聞こえ始め、夜空に輝くお月様も美しく感じられるのがこの時期ですね。同時に、日に日に暗くなる時間が早くなっていくので物悲しさも感じる頃です。
白露の七十二侯
草露白
くさのつゆしろし。四十三侯にあたります。白露の初侯。
期間
9月7日から9月11日。
侯の意味
気温の低下と共に空気中の水蒸気が冷やされて植物の葉に露が付きやすくなり、その露が白く輝いて見える。

鶺鴒鳴
せきれいなく。四十二侯にあたります。白露の次侯。
期間
9月12日から9月17日。
侯の意味
鶺鴒(せきれい)の鳴き声が聞こえ始める頃。
玄鳥去
つばめさる。四十五侯。白露の末侯。
期間
9月18日から9月22日。
侯の意味
春にやってきていた燕が南の方へ去っていく頃。秋が深まっていることの証明。

白露の行事
重陽の節句
旧暦の9月9日を重陽の節句、別名・菊の節句ともいいます。宮中で邪気を払い長寿を願うために菊を浮かべた酒を飲む風習がありました。節句とは、月数と日数の同じ日で、中国では忌み嫌われる日とされ邪気を払う習慣がありました。また、重陽とは奇数のことを陽数とされ、その中で一番大きい「九」が重なることから重陽と呼ばれています。
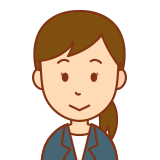
一年の中にはいろいろな節句がありますが一番馴染みのない節句かもしれませんが、高校生の時に習った古文の中に重陽の節句が出てきた記憶があります。
敬老の日
老人を敬い長寿を祝う日として9月15日を敬老の日として祝日とされました。現在は、9月第3月曜日を敬老の日としています。
彼岸の入り
秋分の日を中心に前後3日間を彼岸と呼び、その初日が彼岸の入りである。先祖の供養が行われ、おはぎを食べる習慣がある。この時期に赤く咲く曼殊沙華は彼岸花と呼ばれている。
秋の彼岸に食べるのが、「おはぎ」。春の彼岸に食べるのが「ぼたもち」と呼ばれ、それぞれ植物の萩と牡丹にちなんでいる。

中秋の名月
旧暦では7月・8月・9月が秋に当たり8月が秋の真ん中ということで中秋と呼ばれる。この時期の満月の夜が十五夜(旧暦では15日が満月にあたる)と呼ばれ、秋の澄んだ空気の夜空で輝く満月が綺麗だったことから特別視され中秋の名月として鑑賞しながら宴が催されることが多かった。元は貴族が行った風習であるが、庶民にも広まり五穀豊穣の祈願も加わり、団子や里芋とススキを飾って祝う風習へと変化していった。里芋をお供えすることから芋名月とも呼ばれている。
団子は月に見立てて丸く丸められた団子を十五夜にちなんで三方に十五個積み重ねてお供えをしたり、餡子で巻いた団子を供える場合もある。里芋も皮を剥かずに茹でたものを供えたり、皮を剥いて茹でたものを供えるなど地域によって異なる。

白露に行われる祭り
流鏑馬神事
武家政権の始まりである鎌倉幕府の所在地にある鶴岡八幡宮で行われる祭り。武士の武芸の一つの流鏑馬は走る馬上から弓を射り的を狙う芸。鶴岡八幡宮の流鏑馬神事では約250メートルの馬場で3つの的を射る。

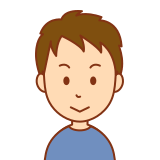
走る馬の上から弓矢を射って的に当てるなんて凄い芸ですね。
この頃の生き物・食べ物
植物
- 白粉花
- 芙蓉
- 秋桜
食べ物
- 鰹
- アワビ
- ししゃも
この頃のことば
- 御山洗い・・・この時期に山に降る雨のことを御山洗いと呼ばれます。雨が山を清らかに洗い流す様を表しています。この時期は秋の長雨前線と重なることから雨も降りやすく、その雨によって洗い流された山の風景が清々しく感じられたのでしょう。
この頃に使える時候の挨拶
- 空も秋色を帯びてきましたが、
- 台風一過の空が殊の外青く澄んで、
- 初雁の姿に秋を感じる頃、