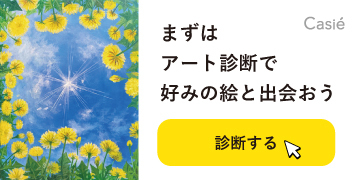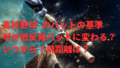四季の違いがはっきりしている日本。そして、昔から二十四節気と七十二侯といった自然と寄り添った生活に関する言葉があります。そのような季節の移ろいを感じながら、少しでも日々の生活を楽しめたらと思います。
大暑
梅雨が明けた後の最も暑い時期。十二節気となります。夏の季節の最後の節気。実際には次の節気の立秋以降も暑さは続いていくが節気的には季節は秋となり、夏としては最も暑い時期とみなされる。厳しい暑さを表す言葉として猛暑、酷暑などがある。立秋以降の暑さは残暑と表現される。
現在の7月23日から8月6日頃にあたります(暦により前後することがあります)
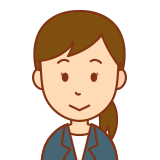
子どもたちにとっては待ちに待った夏休み。太陽の日差しがじりじりと刺すような暑さ、海水浴や川遊びが似合う、文字通りの真夏の時期ですね。

桐始結花
きりはじめてなはをむすぶ。三十四侯にあたります。大暑の初侯。
期間
7月23日から7月27日。
侯の意味
薄紫色の桐の花が筒型に重ねて咲くころ。
土潤溽暑
つちうるおいてむしあつし。三十五侯にあたります。大暑の次侯。
期間
7月28日から8月1日。
侯の意味
夕立が多いこの時期、降った雨で地面が潤い、そこから蒸発する陽炎が立ち上がり蒸し暑さを感じるころ。

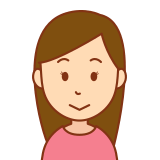
地面からゆらゆら立ち上がる陽炎が太陽の光でメラメラと反射していると蒸し暑さを感じますね。
大雨時行
たいうときどきふる。三十六侯。大暑の末侯。
期間
8月2日から8月6日。
侯の意味
晴れた日でも急に入道雲が発生し夕立がよく降るころ。


大暑の行事
土用丑の日
夏の土用は、立秋の前18日間。この期間の丑の日(年によっては2回あることもある)に「う」のつく食べ物を食べると良いとされてきました。特に、夏の暑さを乗り越えるためにビタミンAやE、タンパク質や脂肪を多く含む鰻の蒲焼を食べることが広まりました。鰻の蒲焼は、関東と関西では開き方が異なり、関東の背開きに対して関西では腹開きで焼かれます。鰻以外には、梅干しやうどんなども「う」のつく食べ物として食べられたりします。

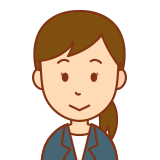
みなさん、鰻を食べて暑い夏を乗り切りましょう。
夏祭り・花火大会
夏の風物詩といえば、花火大会を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。
江戸時代の頃に、各地で夏の邪気払い・病魔払い・厄除けなどを願って行われた祭りと合わせて花火を打つ上げるようになったのが起源と考えられ全国に広まったと考えられます。
コロナ禍で、各地の花火大会が中止されたりしましたが、元々は御払いの願いが込められている花火大会ですので、コロナ禍の終息を願って花火が打ち上げられることも各地で行われています。

大暑に行われる祭り
天神祭り
学問の神様とされる菅原道真(天神様)の霊を慰めるために命日の25日に始まったとされる祭り。各地の天満宮で行われるが、特に大阪天満宮の天神祭りは、日本三大祭りの一つでもある。大阪天神祭りは、旧淀川である大川に神輿を積んだたくさんの船が行き交う「船渡御(ふなとぎょ)」と花火が火と水の祭典と呼ばれ多くの見物客が集まる。
ねぶた祭
青森県地方で行われる夏祭り。地域の訛りによって「ねぶた」「ねぷた」と呼ばれる。
竹や木で作った骨組みに和紙を貼って作った巨大な灯篭のことを「ねぶた(ねぷた)」と言い、地域によって形や呼び方が変わる。
跳人(はねと)と呼ばれる踊り手が山車灯篭の周りを踊りながら町中で曳き回す祭り。掛け声も、青森では「ラッセラー」、弘前では「ヤーヤドー」と異なり、祭りの雰囲気も青森の動的な雰囲気に対して、弘前は静的な雰囲気と異なる。

秋田竿燈祭り
ねぶり流しと呼ばれる邪気・病魔を払う行事が起源の祭り。
12メートルの竹竿に46個の提灯をつるした竿燈を手や肩、額や腰など身体の様々な部位で持ち替えたりする競技が昼に行われ、夜には多くの竿燈が大通りを練り歩き、夜空に多くの提灯が灯されている様は壮観です。

この頃の生き物・食べ物
植物
- 桐の実
食べ物
- 鰻
- 太刀魚
- 穴子
この頃のことば
- 土用・・・一般的に土用といえば夏の土用丑の日を連想しますが、本来は立春・立夏・立秋・立冬の前の18日間のことをいいます。「土用丑」以外には、「土用餅」「土用隠れ」「土用三郎」などの言葉があり、土用餅はこの期間に力をつけるためにつく餅のこと、土用隠れは水温が上がり魚が深部にもぐり魚が捕れなくなること、土用三郎は土用の3日目の天気で豊作凶作を占うこと。
この頃に使える時候の挨拶
- 空高く澄み渡り、
- 降るような蝉しぐれ、
- 寝苦しい夜がつづいておりますが、